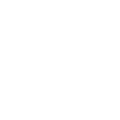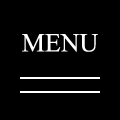子どものコミュニケーション力を磨く
夏休みが始まったので、世のすべてのお父さんお母さん じいちゃんばあちゃん先生方にエールを送っておく
「いい大人になりたい。姿を見せられる大人になりたい」
中学の時の家庭科の先生が、とても怖い先生だったのです。
提出課題はもちろんのこと、
時間、道具の扱い方、全てにおいて徹底しており、「手抜き」を許さない先生でした。
少しでも片付け方がまずいと、
班全員が放課後に呼び出され、
できるまで徹底的にやり直しをさせられるという。
その先生の思い出は「鉄なべの話」など、
他にもいろいろあるんですが、
(鉄なべの扱い方を徹底的に仕込まれた話)
今日話したいのは、そこではなく。
ある日突然、
先生が「数学の先生」に転向したこと、なのです。
密かに免許を取り、準備をしてらしたんでしょう。
春4月。
その先生は、受験学年であるわたしたち中3のクラスに
「数学の先生」として乗り込んできました。颯爽と。
(今でも、先生が教室に入ってきた瞬間の勢いを思い出します。
小柄な身体が前のめりで、教壇まであっという間にたどり着いた、その足取り)
ざわめく教室。
そして、授業は始まり…。
さて。
それは見たこともない授業でした。
それまで、どの数学の先生も…どの「数学のプロ」もあんな授業はしなかった。
先生は、お手製の「黒い箱」を持ってきていたのです。
30センチ✖️20センチくらいの、まさに「ブラックボックス」。
何の内容だったか、正確には思い出せないんですが、
そのブラックボックスに、
「ぽん!」
と数字だかのカードを入れると、横から全く別の数字?記号が「ぽん!」と出てくる。
「ボヨヨ〜ん」とバネのついた数字カードが飛び出てくるのです。
本当に。
その「ボヨヨ〜ん」の仕掛けと、先生の、カードを投入する瞬間の
「ぽん!」
というハリのある声、今でも鮮明に思い出します。
中3を相手に、マジックショーのような授業を始めた先生。
本当に驚いたんですが、けれど…
その時の、自分の表情が想像できるのです。
目を見開いて、瞬きもせずに先生の手元を見つめていたであろう、
中3の自分の表情が。
算数、そして数学の授業で、初めて感じた「楽しさ」。
目と心を奪われる、無垢な集中の感覚。
ああ、自分にも「わかる」かもしれない。
もしかしたら…もしかしたら。
あえて言葉にするとそんな感じでしょうか。
長い間かかって強固に固まった苦手意識と自己否定。
そんな子の心の中に、軽やかな風の吹く間を作るということが。
希望の灯を再びともすということが。
どれだけすごくて、
どれだけ「世界を救う」ものか、なので、わたしにはわかるのです。
(まあ、それくらい数学に関して長いこと心身ともに「フリーズしてた」ということでして)
さて。秋だったか。
外部業者が行うテストで、わたしははじめて数学で80点越えの点をとり。
(わたしにとってはとても大きなことでした)
そして、冬。
受験に向けて、問題を解くことを「楽しい」と感じている自分が、確かにいました。
「先生」のことに戻って。
先生がどうして家庭科の先生から数学の先生になったのか、理由はわからないんですが。
想像ですが、
「自分ならこうするのに」という思いが、
ずーっと先生の中にはあったんじゃないのかな、と思うのです。
ずっと「その道」をどっぷりと歩いてきた者ではないからこそ
見えるもの。持つことが出来る視点。
というものがあるものです。
先生は、それを試してみたかったんじゃないか。
自分の視点と感性を、思いっきり表現してみたかったんじゃないか。
「今、自分がこの子たちに関して見えていて、わかっている視点を使えば、必ずこの子たちの能力を開花させることができる」
という、確信があったんじゃないか、と。
そして、先生は挑戦した。
本当に、エネルギーに満ちた先生であったと思います。
そして、何よりやっぱり、怖い先生でした。
それは、
先生には「誤魔化しが効かない」ことが分かっていたから。
この人の前では、小さな嘘もまやかしも効かない。
いつも、「まっさらの自分」でぶつからないといけない。
自分でないことをやれば見透かされる。
小器用に適当にこなしても意味がない。
失敗しても「自分そのままで取り組んだ」ことをよしとする人だ、
と分かっていたから。
つまりそれは、先生自身が、何より自分自身に対して、
そのように生きていた人だった、ということなんだなあ、
と今になってみると思います。
こうして「その姿勢」を語りたくなる大人と出会えたことは、
幸せなことであった、と思います。
そして、それは、
「今の自分自身の生きる姿勢」
を。
自分自身が言葉の外で雄弁に発してしまっているであろう
メッセージを。
自分自身の姿を問い直すことに、いつもつながります。
(それをあえて言葉にすると、
タイトルの、「めっちゃ素直な」いい大人になりたい!の言葉に
なってしまうわけなのです)
※写真は京都市内の「旧明倫館小学校」。
今は「京都芸術センター」になっています。
この間行ってきたので、載せてみました。
(木造校舎独特の懐かしいにおい)
大人の役割は。
(身近であればあるほど)とどめを刺してはいけないのです
知人の息子さん(小一)が今、
「自分で判断したい期(というのがあるかわからないが)」
を迎えているらしく、曇り空の朝。
「今日は雨は降らないから水着を持って行った方がいい」
(晴れ⇨水泳。雨⇨室内運動)
という、父(知人)、母の全力の主張&ススメにもかかわらず、
「僕は持っていかない。今日はいらない」
と、雄々しく学校に出かけて行ったという。
(水泳バッグ・昭和。で探してみました。懐かしい…)
わたしはその話を、
「やっぱり雨降りませんでしたね。今頃どうしてるのか…」
と現在進行形で知人から聞いたんですが。
1週間後。
その出来事の「オチ」が気になって、聞いてみました。
「で、あの日、帰ってきた息子さん、どんな顔してました??」
知人いはく、
「水泳どうだった?」
と聞いたところ「ニヤッと笑って」
「あった」
と答えた、とのことで。
「軽やかだなあ〜息子さん」
と思いつつ、さらに興味津々だったのは知人の反応で。
「で!?父としてはなんて答えたんです?」
と勢いこんで聞いてみました。
「にっこり笑って『そう』って言いましたよ」
(武士の情け。惻隠の情です、的なことをおっしゃってたような)
この件に関しては、
これで終わったそうで。
(…見事!)
思い出すのは…
こういう時
「ほ〜らみてごらん!」
「やっぱりお母さんの(お父さんの)言った通り!」
「いうこと聞かないから」
「あんたは全く…」
(以下略)
こういうのが、
いっちばん腹が立つんですよね。
反論できないだけに。
雨は降らないまま体育の時間が近づき、
みんなは水泳着を持って来ている。
自分は持ってない。
先生になんと言おう。
勇気を出して歩み寄って、先生に「今日の顛末と自分の判断ミス」
を伝える。
みんなが水の中でキャッキャ言っている、
その水飛沫を眺めながら、
プールサイドで一人静かに体育座りで時間を過ごす。
…
もう、そのプロセスで、
十分に学び、実感し、
「得まくったもの」があるわけで。
(彼は、自分の選択の責任をちゃんと自分で引き受けて、
対処して帰って来たわけで)
それを、
家に帰ってまで「鬼の首でもとったように」
叱られたんじゃあ、
もう、立つ瀬がない。
なので、
「知人は偉いなあ」
「すてきな対応だなあ」
と、素直に思ったのでした。
相手のことを大切に思っていればこそ、
(と書きましたが、案外悔しかったり、「ほら見たことか」的な
自分のスッキリ感を満たしたいだけだよね、とも思ったりするのです)
その一言がつい、出てしまうことがあるけれど。
が、身近であればあるほど、
「とどめを刺してはいけない」
瞬間があるよなあ、
と思った次第です。
そしてもう一つ。
お子さんが、
「自分で選び、その結果と、そこにまつわる考えのプロセスや感情…
全てを全部自分で味わう」
体験を、しっかりと尊重し「邪魔しない」。
そこのところも、「お見事!」
と思った部分なのでした。
「沼ハマ」と「バーストラウマ」
「沼にハマってきいてみた」というEテレの番組が好きです。
10代が、自分の「好き」をとことん追求する番組で、
ここ数回は「鉄道沼」。
すごいと思うのは、「好き」がいとも簡単に彼ら、彼女らの世界を広げ、
人の役に立つようになり、
彼らはやがてそれでしっかりと(楽しく)ご飯を食べるようになるんだろうなあ、
ということ。
さて。
若者が社会へ出てゆく際に、
わたしたちの頃とは比べ物にならないくらい、
「コミュニケーション能力」
が求められていると思える今。
その力が、一定の「定義」があるわけではなく、
実は人により、場により曖昧であり、
そもそも、どうやったらその能力が高まるか、ということもなかなかに「曖昧」。
「これをすれば必ずそうなる」と決まっているわけではない、
ということも、若者を世の中に送りす側の、
「困りごと」の一つとなっている感じがあります。
(と、専門学校にお勤めの知人の話を聞くとしみじみ思う)
そんな中、
企業が(と、いきなり具体的な話になりますが)
どんな若者を採用するか、というと、
「何かに夢中になった経験を持った人」。
「何でもいいのです。
何かに夢中になり、それを通して人と繋がり、何かを創り、成し遂げた経験のある人」
(と、平田オリザさんがセミナーで語っていた)
とてもいい指標だなと。
それが何であれ、
夢中になり、
寝食を忘れ、
好奇心と探究心にとっぷりと浸った瞬間の、あの喜びを知っている子は、
本当に豊かな好奇心に想像力、それに創意工夫の力や
「道なき場所に道を見つけ、開発する」その身に宿しているだろうなあ、
と思うのです。
と、今日はここまでが「前置き」。
もっとわたしにとって興味深いことを書きたいのです。
それは、
「バーストラウマを癒すのは『何かに夢中になる体験』である」
(天外嗣郎 「教育の完全自由化宣言!子どもたちを救う七つの提言」より)
『「バーストラウマ」
出生時心的外傷のことで、無意識である赤ちゃんでも、出産前後の出来事によって、
トラウマ(心的外傷:心の傷のこと)を受けることがあるという考え方です。
(中略)
すべての悩みの根っこに、バーストラウマが関わっており、
またその人の人格にも影響を及ぼすと言われています。
バーストラウマがなくなれば、世界から戦争がなくなるという人もいらっしゃいます。』
https://www.yamanouchishounika.jp/blog_natural/367
(こちらの産婦人科のサイトからお借りしました)
どんなに幸せな環境に育ったとしても、
この「バーストラウマ」だけは、背負わざるを得ない
母体を離れてこの世に出でる際の「初の苦しみ」「分離の恐怖」。
それを、生まれ落ちてからの人生のプロセスで、
「癒し」新たに「自分自身の根っこ=世界の土台と繋がり直す」体験が、
何かに夢中になることを通して、自分の中から湧きいずる
幸福感
自己有用感
自分の感覚や感情、存在への「確固たる信頼」
なのだそうです。
確かに。
自分自身を省みるに、
そういう体験で感じた感覚だけが、自分自身を生かしてきたようにも思うのです。
「何かに夢中になった体験」。
夜も昼も忘れ、
そこにエネルギーを注いだ体験。
中断されることも、否定されることもなく、ただただ「自分の世界」に没頭するという
至福の体験を持つことができた子。
「バーストする感覚」を仲間達と味わった体験をもった子。
そんな子は。
「社会性がつく」
「みんなとうまくやっていける」
「コミュニケーション力がつく」
「発想が豊か」
「粘り強い」
「物事を創造することができる」
…
と。
そんな、わたしたち大人が好きそうな「いい感じの言葉」を超えて、
「安心して、安定して、深い安らぎの中で。
この世界を信じ、人を信じ、自分自身を信頼して、
存分に自分を発揮し、生きていけるあり方」
という、かけがえのない「場所」にアクセスできる力を得るのだ、
という話でした。
そして、わたしたち大人の役割はもう。
子どもが「それ」を体験している瞬間、「止めない」ことなのです。
自分の価値観で否定しないことなのです。
顔の半分が隠された人間が溢れる世界で成長する子どもたち–10年後の彼らの人生と世の中は。
今の新生児〜子どもたちが大人になった時、
人との関係性、人との距離感に関して、
今のこの状況は、どんなメッセージを彼らの無意識層に刷り込むだろう、
と、思うこの数ヶ月です。
他者とは基本的に危険なもの。
何を持っているかわからないもの。
(危険なもの《病氣》をということ)
距離を置かなかればならないもの。
容易に触れ合ってはならないもの。
これらが、
しっかりと「身体に」(=無意識層に)刷り込まれてしまうのでは、
と少々心配なのです。
この「身体に」刷り込まれたものは、
厄介です。
大人になってから、思考で変えよう、打ち消そうとしても、
そう簡単には消えない。
10月末まで金木犀がいい香りでしたが。
香りで、
いっきに秋の朝の冷たい空氣や、子どもの頃の朝の登校風景を思い出して、
つい深々と息を吸ってしまう…
こういうのが、
思いっきり「身体に刻まれたプログラム」が発動した瞬間、なわけですが、
そういうレベルで。
今。
毎日「普通に」目にし、
人と間を取れ!と連呼されるこの状況も、
意識ではコントールできない、深い深い層に染み入り、
子ども達の「感情と身体」の反応を形作るのではないか、
と思うのです。
それは、今のわたしたちには想像もできない。
未だ、誰も体験したことのない反応。
それだけではなく。
「顔の半分が隠された人間が氾濫する世界で成長する子ども」。
客観的に、この単語の羅列を見ただけでも、
ヤバいと思いませんか?
子どもは、「顔認識の能力」を、
多くの顔を見ることで獲得していく、と読んだことがあり。
他にも、想像するに、
微細な表情筋の変化から人の感情をキャッチする能力なども
あるのではないかと。
そういった、
「子どもの頃に発達させなければ、後天的に獲得することは難しい」
能力を育む場面が、
今のこの状況下の子どもたちは極端に減っている、ということです。
今、平田オリザの
「わかりあえないことからーコミュニケーション能力とは何か」
(講談社現代新書)
を読んでいるんですが、
「コミュニケーション能力はつまり『慣れ』。
社会に出るまでに、
「家族」「家族と先生だけ」
「家族と先生と同年齢の『言葉が通じる』仲間だけ」
とのコミュニケーションから抜け出て、
どれだけ『異年齢』『異文化』の中でのコミュニケーションの場数を踏んでいるか、
つまり、それだけ」
(要約&意訳です。
なお「異文化」というのは特別なことでなく、
じいちゃんばあちゃんたちや、
例えばバイト先のおじちゃんおばちゃんたち、そういうものでよいのです)
コミュニケーションは「数」。「場数」。
子どもは「たくさんの人を見て、聞いて、感じて、触れる」
ことからその「コミュニケーション能力」の土台を形作る。
(コミュニケーション能力とはつまり、
「社会とよりよく関わり、自分をしっかりと表現するための
「センサー」の力、ということですね)
ただでさえ「揺らいで」きていた「多様なコミュニケーション」のための環境。
その、最も根本たる、
「土台」(自分に向けられるたくさんの顔を、表情を、笑顔を見る)
の部分までもが、
大きく揺らいでいるのが、
「今」
ということではないか、と思えるのです。
* * *
●●●11月17日(火)20時〜22時●●●
「瞬発力を持って発想し、自信を持ってみんなで創造する
コミュニケーションの力を磨くーインプロワークショップ」
*
このセミナーも、上に書いた「センサー」を磨く時間と
いえるかと。
*
「即興力」というと、
「自分はお芝居をやるわけじゃないから」
「自分には必要ない」
「うちのチームにはそういうものを発揮する場面はないから」
などの言葉を聞くことがあるんですが、
本当にそうかなあ、と思うわけです。
「即興力」とは、そもそも
◆どんな状況下でも
◆フリーズすることなく、
◆自分やチームにとっての最善を見つけ、選び、行動し、
◆自分にとっての最高を「表現し続ける」
力。
これら、何か「特別な」ことを書いているようですが、
そうではなく、
「毎日のコミュニケーション」
は、「これ」の繰り返し、です。
今回のセミナーでは、
即興力の中でも特に大切な土台の力。
「相手の言葉を受け取り、発展させる」
コミュニケーションの力を磨きます。
といっても、
基本ゲームですので、難しいことはなく。
楽しい時間です。
みんなで物語を作ったり、
自分の頭の中に浮かんだことを話したり…
もちろん「正しい答え」なんて、
どこにも存在しない、
その時集まった全員で「創る」セミナー。
柔らかく、柔軟性を持って、
幸せに今日も明日も人と、自分と、世界と関わりたい人は、
どなたでもどうぞ!
* * *
《こんな方に》
・脳の違うところを使いたい
・最近行動がパターン化している
・最近「何か怒ってんの?」と家族からよく言われる
。最近、つい否定の言葉から(「でも」「だって」…)会話に入ってしまう
・最近なんだかものの見方が凝り固まってきたような氣がする
・発言するときに、周りが氣になる
・いろんなことが「パッと」浮かばない
・自分の決断に自信がない
・うだうだと考えてしまう
・無条件に楽しみたい
種はどこかで必ず芽吹く。だからわたし達は諦めずに蒔き続けるのだ
一昨年の夏、
苗を買ってきて、
小さな寄せ植えの鉢を作ったことがあり。
「姫もこう」
と
「ハーデンベルギア」
とあと一つ、名前は忘れましたが、
おしゃれな黄緑のもふっとした植物の3種を植えて、
ベランダに飾っていたのです。
(ちなみに、「姫もこう」も「ハーデンベルギア」も
花屋で初めて知った植物で)
それはそれはお洒落にできたんですが、
いかんせん、
「継続」
させる方法を知らないもので、
結果、
ハーデンベルギアと黄緑のもふもふは枯れ、
姫もこうだけが
「姫」
の愛らしさはどこへやら…
今や、やまんばの頭みたいな状態で、
鉢に生い茂っています。
で、
お話はここからでして。
数日前、
家へ帰ろうと、植え込みの横を歩いていたら…
植え込みの中に、
紫の小さな花がちら…と咲いてるのです。
わあ、可愛い~、と近寄ってみると、
あれ、コレどっかで見たような…
そう。
葉っぱの形といい、
花といい、
長く伸びたつるみたいな形といい、
どう見ても
「ハーデンベルギア」
なのです。
そして、振り仰ぐと植え込みの真上が我が家のベランダでした。
そうなのです!
うちのハーデンベルギアは枯れてしまいましたが、
種が飛んで来ていたようなのです。
(それはどう見てもハーデンベルギアで、
自生するようなものではないだろうし、
やっぱりわたしのだと思うのです)
すごい!と感心するやら
嬉しいやら、
2年も経って、また巡り会えたことが、
とても不思議な感じがするやら…
翌日。
移植ゴテを持って植え込みに行き、
4箇所伸びているハーデンベルギアのうち、
一番小さい一つを掘り起こし、
再び家に持って帰りました。
(あの人植え込みで何してるんだろう、と思われないか、
ちょっと恥ずかしかったですが)
買った時は、ポットに入った小さな苗でしたが、
大地に根を下ろしたハーデンベルギアは、地中に深く深く根を張り…
ちょっとやそっとじゃ掘り起こせないくらいにたくましく。
* * *
という体験談を、
この数日で図らずも2人の方にすることとなりました。
なかなかにたくさんのメタファーに富んだ話だと思うのです。
今、わたしの中でヒットしているのは
「コミュニケーションにおける大人の責任」みたいなもののメタファー、でしょうか。
わたし達のすべての言動が、
「種」
になりうる。
それは、たとえ蒔いた本人が忘れていても、
風に乗って、誰かを伝い、
多くの人の間を旅するだろう。
そして、
どこかの誰かの中に必ず残り、やがて思わぬ力強さでしっかと根を張り、
いつかきっと花を咲かせることもあるだろう。
そうれあればこそ。
だからわたし達は、蒔き続けなければならない。
あきらめず、手を抜かず。
そして、できるならば、良い種を。
美しい種を、巻き続けなければならない。
なんて感じ、でしょうか。
夕方、道端でたくさんの子どもたちとすれ違うとき、
いつにも増して大きな声で「おかえり!」
と言っている自分がいます。
《追記:オンラインセミナー、はじめました》
「おでんはじめました」
みたいなノリですが…。
オンラインは苦手だなと思いつつ、
7月末から試しに始めたZOOMセミナーですが、
やってみると、
オンラインならではの氣軽さの他にも、
オンラインだから出来る様々な可能性を山ほど発見し、
愉しくなってきたところでの、
皆さんへのお誘いです。
このZOOMセミナーは、
毎日のコミュニケーションの場面から一つ、
選んだテーマを真ん中に置いて、
そのテーマを通して、
・人の話をじっくりと聞く
・自分の考えを話す
・自分の感じ方を話す
・共感する
・意見を交わす
・合意をつくる
・自分のストーリー(伝えたいこと)を語る
などなど。
コミュニケーションにおいて必ず発生するこれらを、
少人数で丁寧に体験する時間です。
(もちろん、
その日のテーマについての知識と技術も深まる時間です)
9月のテーマは
●24日「リフレーム」
●29日「イエスアンド」
のんびりお茶を飲むような、
氣の合う人たちと語らいに興じるような、
そんな感覚で氣楽にご参加ください。
それぞれの場所から、
「生活の空氣」と一緒にこの場にINしてくださる方々とつくる、
この独特で貴重な語らいの時間を、
楽しみにしています。
* * *
《セミナー詳細》
①9月24日(木)20:00-21:30
「自分にとっての現実は自分で作る
ー存分に自己を表現して生きるための『リフレーム』力を鍛える」
< /p>
ある出来事があったときに、
どこに視点を向けるのか?
そこから何を見出すのか?
それは、面白いくらい人によって違います。
みんなに共通の「真実」というものがあるのではなく、
実はそれ(真実)は、星の数ほどある。
と、
この数ヶ月、いろいろな人の言動、感情の動きを
見て聴いて感じるに、
あたらめて感じたこの数カ月。
それならば。
どうせなら、自分にとって「力づけとなる」ことを
そこに見出せたほうがいい。
プラスの面を見出せたほうがいい。
そういう視点が大事、
とわたしたちはもちろん知っているわけですが、
「知っている」
ことと
「すぐ出来る」
ということはまた、違うわけで。
それをみんなで練習するセミナーです。
今すぐ、この瞬間からのわたしたちの生活を支える
「思考パターン」
の一つになるといいなと思います。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
②9月29日(火)20:00-22:00
「瞬発力を持って発想し、自信を持って創造する力を磨くインプロワークショップ」
インプロビゼーション【improvisation】
=即興。 特に、即興演奏や即興演劇のこと。
「即興力」というと、
「自分はお芝居をやるわけじゃないから」
「自分には必要ない」
「うちのチームにはそういうものを発揮する場面はないから
(そういう仕事じゃないから)」
などの言葉を聞くことがあるんですが、
本当にそうかなあ、と思うわけです。
「即興力」とは、そもそも
・どんな状況下でも
・フリーズすることなく、
・自分やチームにとっての最善を見つけ、選び、行動し、
・自分(たち)にとっての最高を「表現し続ける」
力。
そして、今ほど「先が見えない」「予測が立たない」
ときはないのでは?と思えるわけです。
今回のセミナーでは、
インプロゲームの中でも、
「即興力」の中でも特に大切な、
「イエスアンド」
(アイデアを受け取り、発展させる)
の力を、言葉を使ったゲームでもって磨きます。
◆インプロで鍛えられる「7つの力」◆
●「自分の感覚を信じる力」
自分の能力や考え、選択を信じ、瞬時に必要なものを選び出す力
●「受け入れる力」
相手の発信を拒否することなくいったん受け取り、そこから創造する力
●「伝える力」
互いの発信を素早く正確に理解し、コミュニケーションをとる力
●「集中する力」
場に集中し、コミュニケーションに必要な情報を素早く正確にキャッチする力
●「転じる力」
どんな状況からでも新しい視点を生み出す力
●「行動する力」
どんな状況でも積極的かつ前向きに動ける力
●「笑う力」
リラックスし、状況を楽しむ力
(「インプロであなたも『本番に強い人』になれる」池上奈生美著より)
* * * * *
参加費はいずれも3000円。
参加ご希望の方は、
https://form.run/@co-co-1600488291
こちらより必要事項をお送りください。
参加費振込のご案内ならびに参加URLを送らせていただきます。
子どもの「機が熟して、溢れる瞬間」が面白いー子どもの成長の醍醐味
いつ行ってもこんな顔でニコリともぜず、抱っこしようとすると全力海老反りで脱走。
黙して決して語らずだった二番目の甥(2歳)が、
寝転がって本を読むわたしの横に、
「すすす…」と、音もなく寝転がって来たのは3月くらい前。
それからは、会うたびに笑顔が増える。言葉が増える。
その「増殖ぶり」は恐ろしいくらいで、
その笑顔全部がもう、
「こんなの生まれて初めて?❗️」
「生まれてきてよかった❗️」
「僕、これを味わうために生まれてきたんだよ❗️」
というセリフが聞こえてきそうな(まだそこまでは喋れないんですけど)
全開の笑顔で。
(天使もここまで純には笑えまい、というような)
そしてさっき弟(彼の父)から
「今、次々に新曲覚えて歌ってるよ〜」
と。
なんでも、「それが結びつき、花開く時」
というのがあるんだなあ、とこういうのを見ているとつくづく思います。
黙して語らぬ間。
彼の中では、忙しく忙しく、いろんなことが起こっていた。
毎日たくさんのものを見て、聞いて、味わって、
吸い込んで…
そして、彼の中にあふれた「それら」が
ついに「線を超えた」。
たくさんの断片は彼の中で繋がり、はじめて意味をなし、
一つの世界となって
今、一氣に溢れ出る。
甥の笑顔は、世界と自分の関係をはじめて認知した人の
喜びに溢れているように感じます。
人は、こうやって何回も、生まれ、世界と
さらなるフェーズで出会っていくんだろうな、と。
…負けてられない(笑)
(この子たちが大人になったとき、みずみずしい人間でありたいものだと)
(追伸:あと、とにかく子どもは待たなきゃいけない。
大人も同じかな。大人も、規模は違うけれど、上記の流れで
成長していくんだろうなと。
何より、大人は自分自身を待てないと、ですね)
※人の子の顔を出すのもなんなので、絵にしてみました。
若者に(人間に、でもいいけれど)「美しい言葉」が必要なわけ
知り合いのコーチから
「こうこさん、おはよー
朝からきいて、泣きそうになって力出た‼️よかったら」
と、送ってきたのがこの曲。
彼女に返した返信をそのまま載せます。
『山ほどの、若い人たちの
心の中に、身体感覚としてある感情と結びついた感覚を、
ピタリと。
いや、それ以上のところで言葉にしてくれているんだろうなあと。
自分で適切な言葉として出せなくても、
渦巻く幾万の思いがある年頃。
こういう歌を聴いたり、
歌ったり、
そういうのが本当に大切な年頃なんだろうなあと。
また、
この声のなんとも言えない響きや、全身から出ている感じもいいですね!
曲を聴く子たちも、
自分はこんな声は出せなくても
一緒に共鳴して身体と心を震わせられるなあと。
【中村注:人にはミラーニューロンがありますから、
自分がその行動を取らなくとも、その「感覚」を全身に満たすことができる。
清々しさ。エネルギー。殻がパキン!と割れて、
自分がわ〜っと世界に広がる感覚)
そして、そういうものを起こせるのが
「優れた歌、優れた言葉」のポイントだろう、と】
以前、
中学校で「合唱コンクール」があるわけ、というのを
読んだことがありますが。
本当に、若い人たちが「美しいものに触れること」の意味を改めて感じています。
(「なぜ学校で芸術が教科としてあるのか?」)
https://ameblo.jp/businesskouko/entry-12393202530.html
ところで、
なんの予備知識もなく聞いて、これ、オリンピックに向けての歌?
と途中で思ったんですが
甲子園なんですね。
…これ、
どっかで書いていいですか^0^??
こちらも昨日梅雨が上がりました!』
*
*
*
(「これ、どっかで書いていいですか?」
「これ、どっかで喋っていいですか?」
「使っていいですか?」は私の「口癖」です。
私のクライアントさん方は、いつも弾丸のようにこの言葉を浴びせられています^^)