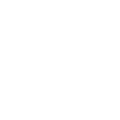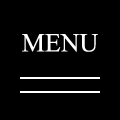朝ドラ「らんまん」を見ていて、ふと上の言葉が浮かんだんでした。
主人公の描く精密な、精密すぎる植物の絵。
どんな気分であっても、どんな状態であっても、
そこに植物があったらつい嬉しくなり、じっと見てしまう。
話しかけてしまう。
(牧野富太郎博士自身がそういう人だったんだろう、
とご本人の笑顔の写真を見て思うことなのです)
「愛」というものの土台は、
「見ている」
ということなのだと思います。
「まなざしを注ぎ続ける」と表現した方がいいでしょうか。
(または「あたたかい観察」)
そして「ものすごく細部まで見てとることができる」
「氣づくことができている」
ということ。
いつも「見ている」。
細部に至るまで「見ている」。
細やかに「見ている」。
朝昼晩、春夏秋冬、ずっと「見ている」。
朝と夕の変化。
季節ごとの変化。
どんな細かいところまでも、
繊細な葉の筋の一本までも「氣づくことが」できる。
そして、「それ」のありのままの姿、
ありのままの特質を心から愛で、賞賛し、尊敬し、慈しむ。
*
他者から自分に向けられる言葉や行為に対して。
または自分自身から発せられる「誰かへの言葉や行為」に関して。
それは「愛から」のものなのか?
そうでないものなのかを見分けるには、
上に書いた「土台」が根底にあるか?あってのものか?
を判断基準にすればいい、と思います。
「愛」からのものとは、
・いつも見ている、しっかり見ている(あたたかい観察)
・細部まで見ることができている
・対象のありのまま(本質・特質)を見てとれている
・ありのまま(本質・特質)への尊敬、賞賛、慈しみがある
・ありのまま(本質・特質)をこそ、大切に保ちたい、
伸ばしてあげたいと思う気持ちがある
それ以外のものがもし入っていたら、
それは「愛」ではなく。
「自分の心配、自分の不安、自分の欲、自分の願望、自分の理想…」
を押し付けられているのかもしれない&押し付けているのかもしれない。
と疑ってみてもいい。
牧野富太郎博士の植物の絵。
あの細やかさ、あの緻密さ、
あれは、「愛」以外の何ものでもない。
ただただ、対象をありのまま、真の意味で「愛した」。
愛を持って「見続けた」からこそ描けた人の絵なのだと感じています。