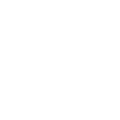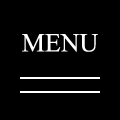数日前、会話をしていて「聞かれてないなあ」とモヤモヤすることがあり、
すっかり元気がなくなってしまったので、
(わかりきっていることですが「聞かれてない」「受け取ってもらってない」
という感覚は結構「来ますよね」心に)
みんなで再確認しましょう‼️
まず、前提として、
「コミュニケーションはキャッチボール」。
よく聞きます、知ってます、と思ったあなた。
この「キャッチボール」が本当には「出来ていない」こと、結構多いのです。
以下、
わたしが研修で実際にボールを使ってやる
「コミュニケーションはキャッチボール」のエクササイズを、言葉で書いてみます。
さて、「心地よいキャッチボール」のルールとは。
❶心地よい速度の(受け取りやすい)ボールが
❷一回に一個、こちらに飛んでくる
当たり前ですね。
当たり前なんですが、ボールを「言葉」に置き換えると。
「ものすごい速さのボールが」
「一度に2〜3個飛んでくる」
ようなキャッチボールを平気でやっている人がいたりします。
(ボールだと、そんなことしたら「何かの特訓か??」ですけど、
「言葉」だと平気でやってしまったりする)
さらに。
心地よいキャッチボールのルールは続く。
❸自分が投げたボールを「相手が受け取った」ということがちゃんとわかる
これも当たり前ですね。けれど、これを言葉に置き換えると、
「反応がない
(うなづきがない、相槌がない、目が合わない、受け取ったよというメールがない…)」
とても「不安になる」やり取り、溢れているんじゃないでしょうか。
さらに。
❹投げたボールが相手から自分の手元に返ってくる
この❹までを完了して、初めて「コミュニケーションが完了した」
ということになります。
ここまでをやって、一つのコミュニケーションが終わる。
「相手にボールを返さない」
「もらったボールを一人持ちし続ける」
そんなキャッチボールは「ありえない」わけですが、
これが言葉だと、ある。とてもある。ものすごくある。
「返事が返ってこない」
というわかりやすいものから、
あなたが一生懸命話した内容に対して、
「へえ〜、そうなんだ」
の一言で、
⚫︎「ところでさあ」とあとは自分の話に持ってかれる…
⚫︎「それってこうなんじゃないの」
と断定される、判断される、ジャッジされる、
欲してもいない(合ってもいない)「答え」を返される、などなど。
(ああ、なんて悲しい)
さて。
心地よいキャッチボールのルール。
❶心地よい速度の(受け取りやすい)ボールが
❷一回に一個、こちらに飛んでくる
❸自分が投げたボールを「相手が受け取った」ということがちゃんとわかる
❹投げたボールが相手から自分の手元に返ってくる
ボールを「言葉」に置き換えて、
自分が毎日、どんなふうに、どんな速度で、どんな投げ方で
「言葉というボールを」相手に向かって発しているか、
そして、どんなふうに受け取り、相手に返しているか。
双方にとっての快適な「リズム」はあるか?
改めて、「イメージして」みてください。
あなたと大切な人との対話において、
きっと、大いに発見するところがあるのではと思います。
「コミュニケーションはキャッチボール」
このことが、しっかりと「身体で」実感出来ていると、
コミュニケーションというものが、
「なんて言えば…」
とか、
「どんな言葉を使えば…」
以前のものであって、
表面的なハウツーのみでは成り立たないものだということが、
よくわかるのではないかと思います。