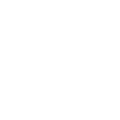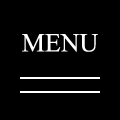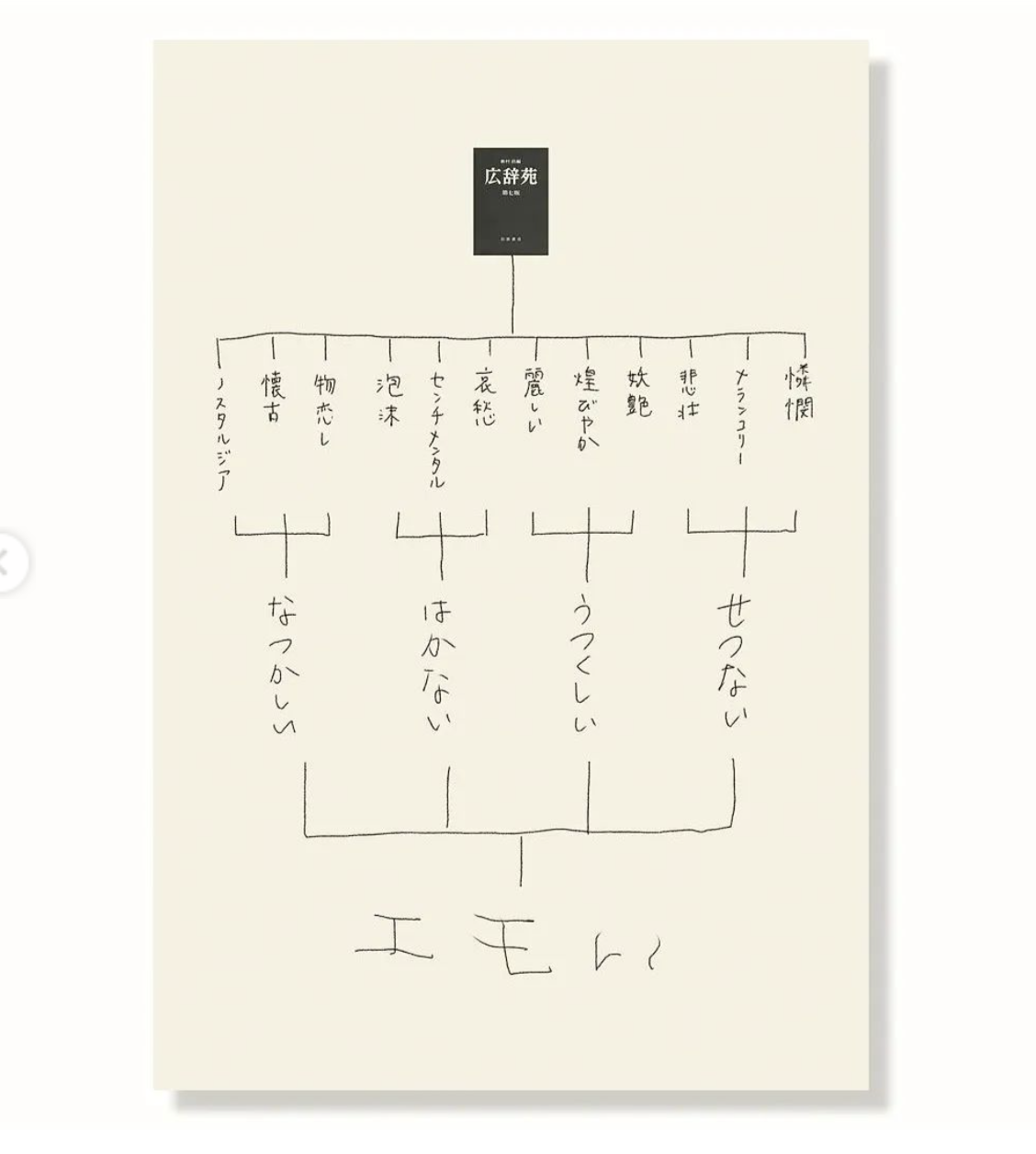今日から浴衣を着てみたんですが。(7月の声を聞いた途端、うずうずしてしまい)
半分は趣味、半分は仕事でしょうか。
話は飛びますが、
偶然「フットケア」の特集番組を見まして。
足の不調(外反母趾や、巻き爪、魚の目、たこ…や何やかやで痛くて歩きづらい)
をどうケアするか、という話と、
予防として、そもそも「そうならない」ための「靴選びや歩き方」、
といった内容だったのですが。
それを見ていて、思ったことは、
「なんだかんだ言っても、わたしたちは『靴』に馴染んでいないし、
『靴で歩く』ことにも扱いにも慣れていないのだな」
ということでした。
靴を履き始めて160年(やっと)。
身体なんて、そんなにあっという間に変わるものじゃない。
一体、何人の日本人が足のため、
身体のための「靴の正しい選び方」「扱い方」をちゃんと、
お味噌汁を作るくらいの「当たり前」レベルで
知っているだろう、出来るだろう、と改めて思ったのでした。
で、
ふと思い出したのですが。
相当昔の話なんですが、何かの番組で、
「オードリー・ヘプバーン」の問題が出ていて、その問題が、確か
「オードリーが小さい頃、足が綺麗にちゃんと成長するように親ががやったことは?」
というような問題だったのです。
で、いくつか選択肢があって、
答えは「足首まである編み上げ靴を、紐を締めてしっかりと履かせる」
だったように覚えています。
今思えば、向こうの人たちにとって、そういうのは、
至極当たり前のことなんだろうなあと。
で、日本人なのですが。
では、草履や下駄を履き、畳や板の間で「座して」暮らすことで
昔からご先祖が馴染んできた、
「身体の使い方」
は身体にちゃんと息づいているか?というと、
それももう、ない。
そして、今の若い子たちは「蹲踞(そんきょ)」ができず、
丹田の場所がわからず(こういう役者の卵の子に会ったことがある)、
浴衣の帯をウエストで結び(男の子です)
腰を立てて姿勢をキープできず。
しかも衝撃だったのは
10代から「尿もれ」を起こしている女の子がいると。
(骨盤底筋が弱いのが原因らしいのですが、
これは、和式の生活をしていればごくごく自然に鍛えられてきたものなのだそう)
で。
「どこへ行く日本人」
「どうする日本人」
と思ってしまったわけなのでした。
もう「和」は捨ててしまった。
どっちつかずで何者でもなくなってしまうんじゃないか?と。
フラフラと。
あっちへいき、こっちへいき、何が正しいのか?
何を軸にしたらいいか、とても深いところでわかっていないというか、
なくなってしまっている。
その精神も、「よって立つ『よすが』がない」感じ。
それらは、こういったところにも
(生活様式、身体の使い方が伝承されていないところにも)
その原因はあるのではないか??
とずっと以前から思っているのです。
身体の軸と精神の軸はしっかりと繋がっているわけですから。
そんなことを考えつつ、浴衣でここに座っている今。
(近所の人と、カフェの店員さんから
「何かお稽古ですかっ😃!」と声をかけられつつ)
それにしても。
「和のよそほひ」って、背中を丸めようがないなあ、と
(下腹が定まって楽だよなあと)。
それに、下腹で楽に全身を支えられるので
(帯で下腹をきゅっと締めてますんで)
肩に余計な力が入らなくて、大変よろしい。肩こり防止に。
日本人の中心は「肚」なんだなと。
頭(思考)と、胸(感情)と、肚(意思・精神)。
最終的には、腑に落とし、決断し、
そして「肚からの声」で伝えるのが日本人だったんだろうなと。
そんなことをつらつらと思っているところです。