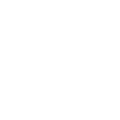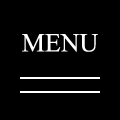今朝ほど清里の街の再生をする人たちの番組を見ていて、
なんだか悲しいやら切ないやらの気持ちになっていたところでした。
清里高原がブームになった時、
あそこに一斉に押し寄せていた若者たち
(パステルカラーの服を着て「聖子ちゃんカット」をしていた人たち)
とわたしは大体同じ年代なのだけど。
当時から幕末オタクの神社仏閣好きということもあって、
あの、キッチュな偽物(いかもの)チックな清里の雰囲気に、
なんとなく
「恥ずかしいな…」
という感慨を持ってみていたのだけど。
けれど、そんなわたしですらパステルカラーのものを、
何かしら身につけていたように思うので、
時代?流行り?空氣というものは本当に恐ろしい。
その番組には、清里の地元の人たちが描かれていたのだけど、
みるからに「本当に難儀だったろうなあ」と想像するに十分で。
ブームの時。
外からどっといろんな人たちが入ってきて、
「キッチュな」「イカものな」(言い過ぎ?)
お店をどんどん建てて、人が集まって。
その雰囲氣に乗って、地元の人たちも同じようにして。
「ああすれば儲かるのだ」「乗り遅れるな」と。
けれど、ブームが去った途端に、
外から来た人たちはさあっと潮が引いたように清里から去っていき。
後は、食い荒らされた土地に、
歯抜けのような空き店舗だらけの街。
その中にぽつねんと取り残された自分の店。
辛かったろう。
悲しかったろう。
歯痒かったろう。
絶望したろう。
と思うのだ。
父親からのレストランを引き継いだ一人の男性。
父親の工夫と努力で繁盛していた店を、
ブームに乗って改築し、席数を増やし、
効率優先で多くのお客を捌くために冷凍食品を使うようになり、
そしてブームが去った時、お客も去っていった。
お店は負債を抱え、閉店。
今、がんとして加工品を使わず、
パスタ麺を自分で打ち、カフェを続けるその人。
(喉から手が出るほど加工品を使いたいけど、でも使わない、と言っていた)
きっと彼は深い後悔の中で、この30年間
「自分とは何か?」「自分はどう生きたかったのか?」
を探し続けてきたのではないかと思え。
「清里だからお客が来るんだと思っていた。
でも、そうじゃなくて、いいお店があって、
それがたまたま清里にあった、じゃなきゃいけないんだ」
いうのはその人の言葉。
清里(のような、もしかしてあちこちにあるかもしれない街)が再生するとき。
今度こそ、その土地に根ざす人たち、一人一人の意思と、知恵と、
まことなる自立の心、
「こうしたい!」
「これが自分たちなんだ!」
「これを大切にするんだ!」
という心からの思いで街が息を吹き返すとき。
日本も真の意味で再生していくのではないか?と思える。
それは結局、
わたしたち一人ひとりの心の中、在り方と無縁ではなく。
(全てはフラクタル)
清里の人々だけでなく、
この大きな変化の時、
わたしたち日本人一人一人に、刃のように突きつけられ、
問われている、
大きな「喫緊の課題」なのだろうとも思える。