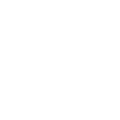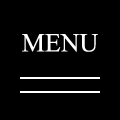秋田で仕事をしていた姪からのお土産が届き、
スモーキーで味わい深いいぶりがっこや
「かき飴」
(牡蠣エキス入りの飴。甘いのに海産物の味もちゃんとする😳)
など、
南国人からすると大変珍しいものがたくさん入っていたのだけど、
その中でも見た目のインパクト大(だい)!だったのが、
『なまはげのおくりもの✨✨』
という秋田のお米で作ったサブレで、
ふわっと軽いお味で大変美味しかったのですが、
偶然にもその日の夜、
「なまはげの社会適応化」
というのを番組でやっており、
なまはげサブレの興奮も相まって、興味深く見たのでした。
「泣く子はいねが〜👹」
と、大晦日の夜、家を回り、
子どもに大きなトラウマを残す「ナマハゲ」。
(確かに、映像に残る昔のナマハゲは激しい!これは子どもは怖いだろうなあと😊)
これが、時代とともに、今風にいうと
「コンプライアンス遵守(笑)」
な言動に変わり、
(入り口でインターホンを押し「はいってもいいですか?」と聞き、
靴を脱いで揃えて上がり、そこから「泣く子は…」とナマハゲモードに入る^^)
担い手不足に伴って、外国人のナマハゲが生まれ、
さらにはコロナによって、
「窓越し、ガラス越しのナマハゲ訪問」
に至る、という…
まさに、社会適応化の「歴史」。
お笑い芸人さんの番組なので、
その「変遷」につい笑ってしまうのだけど、
その向こうにはどうにかして「ナマハゲ文化」を伝承したい、
しなければ、という男鹿半島の大人たちの願いと工夫がひしひしと垣間見え。
サブレの袋のインパクトある可愛らしいナマハゲを見ながら、
「こんな苦労と歴史があったのか…」
と、色々と感じ入ってしまいました。
ここでふと思い出したのは、長崎くんち。
たった2年休んだだけで(コロナで)
「伝承」が危うくなってしまった町がある、という話を思い出し。
(知識と技術を「つなぐ」ために大変な苦労をすることとなった人たちの話を見たんでした)
なくなってしまう(途絶えてしまう)ということは、
食であっても風習であっても、「モノや行事がなくなったね」では終わらない。
とても多くの、たくさんのもの…
つまり、そこに込められ、先人たちが大切にし、なんとか繋いできた、
「心」「価値観」「精神性」までもがもはや伝わることのない、
失われたもの、になってしまうということなのだ、
(だからこんなに努力しているのだ)
と、そのくんちの番組を見た時に、強く感じたのでした。
さて。
これから、ナマハゲにどんな将来が待ち構えているのか?
それは分かりませんが、
それでも。
これからもナマハゲに幸あれ!
男鹿半島の皆さんに幸あれ!
日本&世界中の、
「自分たちの土地の伝統、文化、風習」を大切に守り伝え、育て続けるすべての人たち
(つまりわたしたち一人一人の中にあるその心とDNAに)
幸あれ!
と心から思ったのでした。