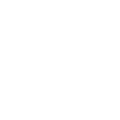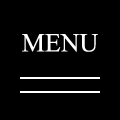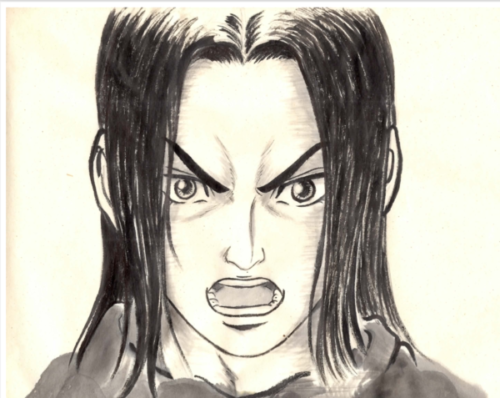アニメから学ぶコミュニケーション
あなたの魂に、『檄』!ーアニメ「キングダム」に見るプレゼンの構成
今、アニメ「キングダム」を日々見進めているのだけど、
とにかく『檄(げき)』がたくさん出てくる。
(そして、この、将兵を奮い立たせるための演説を『檄(げき)』というのだと、
わたしはキングダムで初めて知った。檄を飛ばす、というのはこれのことなのねと)
秦の若き王、嬴政(えいせい)が、
秦国の最後の砦、「蕞(さい)」の民衆に檄を飛ばす回(第3シリーズ19話「政、語りかける」)は、
テレビシリーズで放送された時のをちゃんと録画して保存してあるくらいに、ちょっとよかった。
いずれプレゼンを扱うセミナーで使えるネタになるであろう、
と保存しているわけなのだけど。
嬴政(えいせい)の檄。
「人の心を奮い立たせるために、何が必要で、人の心のありどころを何を結びつければいいか」
をよくわかっている檄だと思うのだけど、
こういう場面で、いつも思うのはまず「檄の振動」について。
キングダムで、大将が「檄」によって動かす兵の数は、桁が外れている。
数百から、多い時は数万。
この場面を見るたびに、ある本で読んだ、一つの場面を思い出す。
対談者が「武者振るい」について語る場面だった。
「武者振るいとは、
武者(大将)が本当に、身体から出す振動なのだ。
『震え』なのだ。
その『大将の震え』(恐怖からのではない。もちろん)
が甲冑の錣(しころ)やなんかで増幅され、周りの将兵に伝わる。
それが、次々と伝播し、瞬く間に数万の兵に伝播し、兵は一つの塊となる。
一つの巨大な塊となって大将の意のままに動く『生き物』となるのだ」
と。
そんなような内容だったように思う。
(文言は細かく覚えていないので、こんな感じ、ということで)
「カタカタカタ…」
「震え」が甲冑を伝わって広大な集団の中をざああっ…と広がってゆく、その感覚を肌で感じた気がして、
ゾワっ…となったものだった。
さて。嬴政(えいせい)の檄に戻って。
嬴政の檄は、古今東西、優れたリーダーが人の心をつかみ、
一つにする時に使う「セオリー」を踏襲している(と思う)。
以前、プレゼンセミナーのために、北条政子の「檄」を調べたことがあったけれど、
彼女も同じような「構成」で檄を飛ばしていた。
それは、
「時間に橋をかける」
構造なこと。
過去、そして今現在を生きている自分、そしてさらには未来。この3つの時間軸をつなぐ。
人々の意識をそこに向けさせる。
「今だけ、自分だけ」ではなく、
滔々と流れる時間の営みの中に自分は生きており、
受け継ぎ、そして次へと手渡さねばならない「何か」がある。
そこに、人々の意識を向けさせる。
そこに、人は、ただ日々をせっせと生きている時にはなかなかアクセスすることのできない、
「自身の深い、生きている意味」を見る。
きづく。
自分は、たった一人、切り離された自分、なのではなく、
「バトンの担い手」であり、
今この瞬間を「代表選手」として生きているのだ、という事実。
その「時という大河」を大きく俯瞰して人々に見せ、つなげ、自覚させる。
嬴政(えいせい)は、
ほんの短い時間で三万の民衆に対して(兵ですらない、老人女子どもに)それをやってのけるのだ。
https://www.youtube.com/watch?v=exDRtE79ojE
(19話の「檄」。音声のみ上げている人がいたので貼ってみます)
今日のまとめ。
「それ」(発進したもの)がどこまで届くのか?
それは、発信者の「イメージ」の強さ、豊かさ、深さ、高さによって決まる。
それはイコール、その人の身体状態を含む「プレゼンス(存在)」の強さ、豊かさ、深さ。
それは、今も昔も変わらない。
古来、武将たちは、
言葉を発しつつも言葉をこえ、時間を超えて、
「あなたの魂に、『檄』!」
そう思っていた違いない(こういう言葉で意識はしなくとも)
と思うのだ。
(そして、この言葉。「いい言葉を思いついた」と今感じているところで、
自分のキャッチフレーズにしようか、と思ったりしているところなのです)
その差は「つながりを作る力」の差ー炭治郎と鬼たち
鬼滅の刃の「鼓屋敷編」「那田蜘蛛山編」を見て思ったのだけど。
炭治郎の力の源。
いざ、という時に危機を切り抜ける、その力は一言で言うと
「つながりの力」
がもたらすものだな、と。
決して万能ではなく、ヒーローでなく、
切れば血のでる身体を持ち、「努力の人」以外の何者でもない炭治郎が
持っている能力を何かこう、超えて「力」を発揮するとき、
炭治郎の背後には、家族をはじめ、
今はいないけれど彼を支えている人たちの存在があり、
彼も、そこへの思いを原動力に力を発揮する。
かえって。
「鬼」というのは、
「つながりをつくれなかった(つくることに失敗した)人たち」
ではないか、とも思うのだ。
鼓屋敷の鬼は、
自分の書く小説を否定されて、
つまりは、
「自分が世界と関わるために
(自分が自分であると世界に向けて表現するために)
一番大切にしていた部分」
を失ってしまった。
もちろん、否定の言葉を受け取らない選択肢もあったろうけれど、
彼にはそれができなかった。
(もしあれが炭治郎だったら、きっと受け取らなかったろうとも思うのだ)
那田蜘蛛山の鬼は
親から受け入れられていないと思い込んで、
親を殺してしまった鬼。
そして、「本物の絆」とやらを探して、無理矢理に恐怖で周囲を従わせて
「家族ごっこ」をしている。
それでも孤独は埋まらず、ますます残忍な支配に走る。
世界が自分に背を向けている、と感じたとき。
心が折れてしまったと思ったときに。
人をこの世界に(人間に)とどめるものは何か。
(「鬼」を呼び込むことなく)
この世界を生きるわたし達に、
炭治郎のような身体的な危機は訪れないが、
心の危機はいつでも容易に訪れる。
現実世界に鬼舞辻無惨はいないけれど、
誰でも、ちょっとしたきっかけで、容易に「鬼」になってしまえるのだ、とも思う。
そんな危うい瞬間に、人をこの世界に繋ぎ止めるものは何か。
自分を慰撫し、癒す力。
「いろいろあるけれど。そして、こんな小さな(どうしようもない)
自分ではあるけれど、それでも明日も生きてみよう」
と、踏みとどまらせる力。
それは、「つながりの力」しかない。
それでしかあり得ない、と思うのだ。
「自分はつながっている」というしっかりとした感覚。
家族、友達、自然…形あるもの、ないもの、なんだっていい。
自分が生まれ落ちたこの世界との絆。
善逸も伊之助も。
彼らの人生の中での、数は少ないけれど、涙が出るほど大切な関係性が、
実は彼らを生かしていることが丁寧に描かれる。
けれど、鬼たちには、人生において残念ながら「それ」がなかった。
気づけなかった。
鬼と炭治郎(&禰豆子)を分けたものは、
ただそれだけにも思えるのだ。
炭治郎は、その素直な心根で今日も「つながり」を作り続ける。
彼はそれが持つ力に微塵の疑いも持たない。
日本のアニメが世界の子どもに与えたよい影響、という記事を昔、読んだことがある。
「信頼」「仲間」「つながり」「違う個性同士の協力」といったものが、
根底のパターンとしてある、と。
それは、欧米のものとは少し違うらしい。
「日本のアニメを見て育った世界の子達の心にそれらの価値観が染み込んでいく。
それは世界平和に貢献しているのではないだろうか」
と言った内容だった気がする。
鬼滅の刃の世界観は徹底的に「残酷」。
人は惨殺され、鬼はどこまでもこれでもかというくらいに気持ち悪い。
炭治郎の人生も、お話にならないくらい可哀想で、過酷なものだが、
それでも描かれるのは彼の太陽のような心であり、
彼が醸し出す「泣きたくなるような優しい音」であり、
倒すべき鬼にまで向けられる彼の慈愛の情だ。
壮大なるメタファー。
それはこの「変わりつつある世界」をこれから長く生きていく子どもたちへの
「贈り物」なのかもしれない。
炭治郎の瞳に、声音に、笑顔に、言葉に。
大袈裟だけれど、わたしは希望を見る。
近づき、ふれあい、手を取って、大声で笑い合う。
天を仰ぎ、思いっきり呼吸する。
そんな、人として生きるに最も必要不可欠な
「つながりを欲する」自然な欲求すら抑えられ、
成長を強いられた世代として大人にならざるを得ないかもしれない。
それが、身体に、精神に、彼らの無意識にどんな影響を与えているか、
今、この時点では誰にもわからない。
はかることすらできない。
そんな「かつてない(誰にも予想できない)世界」を、
これから生き続けなければならない子どもたちの無意識に。
どんなに過酷でも、人は潰れない。
人の心の力はそんなものではない。
そう、
「今日も、これからも、折れていても、挫けることは絶対にない!」
と。
人は、
何があっても、どんな状況であっても、
前を向いて生き続けることができる。
人を愛して、最善に向かって生きることができるのだと。
鬼滅の刃という世界観は、
全身全霊で、そう大声で叫んでいるように思える。
答えは外からは与えられない。
力はいつも、自分の中にその源がある。
しっかりと呼吸をするのだ。
呼吸はウチと外(自分と世界)をつなぐ。
「全集中」で。
自分の身体を取り戻せ。
自分の軸を取り戻せ。
世界とのつながりを取り戻せ。
そして、
「前へ。前へ。進め」。