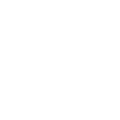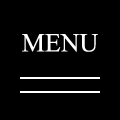というテーマで先日書きましたが。続きです。
* * *
「身内が餃子のお店を始めたんです。よろしければ、お裾分けを…」
というなんともありがたいお話をいただき、
ありったけの保冷剤を詰めた「ミニ保冷バッグ」持参で、知人と会ったのが昨日。
(なんでも、美味しく焼くためにはカッチコッチの冷凍のまま
フライパンに置くのがポイントだそうで、「溶け」をなんとしても阻止しなくては、と)
さて、
知人と過ごした楽しい数時間の詳細は省き、
夕方5時半。
家に帰りつき、速攻でフライパンを出し、「焼き」の作業に入りました。
「焼き方」(絵付き)の説明書をみながら、最新の注意を払い。
(何せ、いつもの餃子とは違います。餃子専門店の餃子!期待大なのです)
「フライパンに大さじ一の油を敷き、
プライパンを熱して、その後弱火にしてから餃子を間隔を取って並べ…」
説明書をガン見しながら頑張ること10分ほど(かな?)
いい色に焼けた餃子(形も美しくキープ)は、
カリっとした歯触りと、その後の「パシュ…」感(旨み広がる感)。
…美味しかった。
とてもとても美味しかった。
そして、先にも書きましたけど、こんなにうまく焼けたのは初めてで(喜)
で、焼いていて、本当に「焼きやすかった」のですが、
そのポイントが説明書に書かれた「音」だったのです。
「七十度のお湯を餃子が5ミリほど浸かるくらいに入れ、蓋をする。
その音が、
『グツグツ、ブクブク』から『チリチリ、パチパチ』になったら蓋を開けて水分を飛ばし…」
時間指定などよりも、
ずんとわかりやすい。なんて「安心ガイド」。
さて。
この日、わたしはこの餃子お裾分けの知人に「玉ねぎ」を進呈したのですが、
(いつも書きますがうちの姉の無農薬農園謹製)
その際、とある食べ方をして欲しく、
直径15センチもある大きな玉ねぎを一つ、入れておいたのです。
その「食べ方」と言うのは、「玉ねぎステーキ」なのですが。
直径15センチを横一文字に切って2分割。そのままフライパンに置いて豪快&丁寧に焼く。
そうすると、
塩胡椒&バターでも美味しいし、
花がつお&ポン酢でもいける。
試していないけれどきっとチーズ&トマト系ソースもいけるぞ!
という…
とろっとろの玉ねぎの甘さを楽しめる、最高に美味しい一品になるのです。
さて。
夜、知人からメールがきました。
今日の御礼とともに、
「玉ねぎステーキ、わたしの腕がまずく、
火が通らないところが少し残ってしまい…火の通ったところはめちゃくちゃ美味しかったです!」
…ああ、知人よ。
それはあなたの「腕」のせいではなく、明らかにわたしの「説明不足」。
焼く感覚は「トロトロ」と。
(中火の弱火とか言ってしまったんですが、家のコンロによってそんなの違いますもんねえ)
断面は「ふやっと」。
側面は「ツヤツヤ」。
全体的な感触は「ややくたっと」。
…
こういう「感覚」はなんにも伝えなかったなあと。
どんなデータよりも確実に、
(いえ、データはすごいし、大切なんですけど)
わたしたち日本人に、
「ものすごく膨大で繊細な量の情報を一瞬にして伝達してしまう」
「擬音語、擬態語、擬声語」という話でした。
そして。
日頃、「データ重視」。理路整然と語るのが当たり前、という世界に住んでらっしゃる方。
オノマトペなんて子どもっぽい、と言わず。
フォーマルじゃない、なんて切り捨てず。
バランスをとりつつ、少しだけこの、豊かな「オノマトペ」の世界を
挟んだりしてみてもいいかもしれない、と思うのです。
伝わり方、
伝わる人種、
「あなた」という人の見え方
…
などなど。
いろんなところに案外「可能性を開く」ものになるかもしれない、と思います。