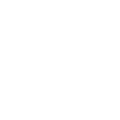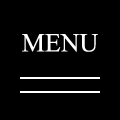2週間ほど前、ちょっと動くと途端に首がバリバリと痛くなることが数回あり、
考えた挙句、
「重い荷物を腕だけで持ち上げようとする」
のが原因だなあ、と気づきまして。
筋力の衰えに反して(筋力が落ちているのも問題ですが!)
持ち歩く荷物の重さは変わっていないもんなあと。
そうなると「腕から動く」のをやめる必要がある。
腕の力のみに頼るのをやめて、
「中心から動く」。
「古武道の身体の使い方を介護に活かす」
的な番組で見た知識を思い出しながら、
臍の下。丹田と呼ばれるあたりから動く。そこを意識して、連動して動く。
を意識しているのだけど、
そうするとだいぶよいのです。楽になった。
(今やすっかり首は元気です)
ここで思い出しているのですが。
ダンスを踊る際に、
「腕を動かす」「足を動かす」というような意識の踊り方だと、
一見、派手に上手に踊れているように見えても、
バタバタした素人くさいダンスになってしまうのです。
身体の中心に落ちた一滴の水。
その波紋が同心円状に全身に広がっていくような感覚で動くといい。
身体の中心で起こった静かな揺れが、
指先、足先までしんしんと広がっていくような動き。
そして、自分の手、足を通り越して、
空間全体に「わんわん…」と広がっていくようなイメージで動くと、とても美しい。
(わたしが教員だった頃の教え子さんでこういう動きをする人がいましてね。
肩先をピクン、と動かしただけなのに、
場の空気を一瞬にして変えるような彼女のダンスを今でも思い出します。
微かな動きの中に、
彼女の中心から湧き出る『律動の強さと純粋さ』を感じたものでした)
そして。
これは身体の動きに限ったことだけではなく。
(と言いますか、一時が万事。共通している)
語るということ。
言葉で伝えるということも全く同じなのです。
自分の中心で起こった振動。(思い。感情。意図)
自分の中心で発生する、
純粋な「最初の一滴」を常に捉え、
そことのつながりを保って、そこから言葉を発するといい。
自分の「最初の一滴」から生まれた振動が、
同心円状に外にしんしんと広がっていくように、
声を出し、言葉が出せるととてもいい。
そこには余計な飾りなど発生する余地は全くなく。
「どう言おう?」
も、
「かっこよく言おう」
「いいふうに言おう」
「ウケないといけない」
「面白くないといけない」
も何も存在しない。
そういうふうに、
「本当の言葉」
「自分の中心としっかりと繋がった言葉」
「その瞬間、その場で、その相手との間にしか生まれない、鮮度100%の言葉」
を出している人や場面に出会うと、本当に心動かされます。
「立て板に水」とか、「話すのが上手いよね」
などとは全く次元を異にする語り手。
そんな人が、いるものです。
(そして、実は誰でもそういう言葉を持ち合わせている)
ちなみに。
わたしは先に書いたダンスの上手い教え子さんの語る様子も好きでした。
ゆっくりと、時間をかけて、言葉を探し出すように話すときの視線。
自分の中に深く降りて、
最もしっくりくる言葉を丁寧に捕えようとするその雰囲気が。
もしも。
言葉が「一語いくら」と値段がついているものであったら、
一瞬たりとも、一語たりとも無駄に使うことはできない。
みんな、自分の「真の意図」を最も表現できるものを、
探して探して、厳選して選び出すだろうなあ、と思います。
そして、
実はそれくらい意識して言葉を使ってもよいのでは、とも思っています。
言葉は確かにただですし、
湯水のように溢れるようにダダ漏れさせても誰も何も言わないし、
いくらだって走らせることができる。
けれど、
「自分の中心と繋がっていない言葉」
は人に届かない時代に、これからますますなっていくように思います。
届かないどころか、
自分の人生に対して。
自分の大切な人たちの幸せに対して。
早晩しっぺ返しが来るような氣すらするのです。