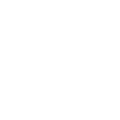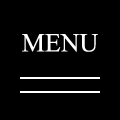「わたしの才能は…」なんていう言い方は、
少々(だいぶ)抵抗のある人もいるのではないだろうか。
いや、むしろ言えない、という人もいるのではないだろうか。
才能・強み。
わたしの専門分野ではそれを、
「放っておいてもついつい勝手にやってしまう、思考パターンや行動」
と定義しているけれど、
最近、いろいろな人の話を聞いていて、
「人には見えていないものが見える(わかる)分野」
という言い方も(わたしにとって)ピッタリくる、
いい表現が見つかったなー、という気がしている。
ある人と、布の話をしていたのだけど、
話を聞いているうちに、
自分がミクロサイズになって、
布の繊維一本一本が交錯している巨大な織りの空間に
ふわんと浮かんでいるかのような感覚を覚えた瞬間があった。
(大昔、こういうSFドラマがあったぞと思いつつ⇨小さくなって人体に入るやつ)
わたしには想像もつかない視点。
見ているところ、見えているところ。
それは多分、その人にとっては「ものすごく当たり前」で、
わたしにとっては新鮮で驚きだらけのものだった。
で、
「才能」に関して、小さい頃伝記で読んだ
「シュバイツアー博士」の話を思い出したんでした。
シュバイツアーは小さい頃から、
オルガンがうまかった。
メロディに美しい和音をのせて弾く。
で、ある日、担任の先生に、
「先生はこうすると綺麗な演奏になることを知らないんだ」
と思い、アドバイスした。
翌日、先生が相変わらず、
片手で(一本指で?)オルガンを弾いているのを見て、
「みんなができるわけではないんだ。
これが普通だと思っていたけれどそうではないのだ」
ということを初めて知る、と。
そんな内容だったかと。
そのことが苦ではなく、ずっとできる。
そして、自分にとって、まるで
「そこに空氣があるように」
「ご飯を食べるように」
自然で当たり前のこと、感じ方、見え方、動き方。
それを「才能」と呼ぶ。
そしてそれは、もちろんあなたの中にも。
あなたの身近な人の中にも。
皆に備わっているもの。
それをお互いに交換しあい、
披歴しあい提供しあってつながっていく。
まるでパズルのかけらのように補い合って丸い豊かな世の中になる。
そんな世の中、
最高じゃないか!と今年、今この瞬間も、ものすごく思っている。
さて。
人はそれに「まみれて」いる時が一番幸せ。
今年、あなたはどれくらいの時間、それに「まみれて」生きるだろう?
あなたの大切な人の「それ」を発見し、
彼が、彼女がそれに「まみれる」ことをどれくらい
サポートするだろう?
どうぞ、今年も存分にやっちゃってください。